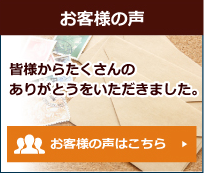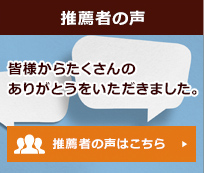故人の遺言書ができてたら?その対応はどうすればいいの?
亡くなられた方(被相続人)が遺言書を作成している場合があります。この場合、遺言書を見つけた後の対応を誤ってしまうと、後々不利益を被ってしまう場合もあります。
そこで、遺言書が発見された場合の対応について解説します。
目次
遺言書の有効・無効の見分け方は?
遺言書は、亡くなった方がご自身の亡くなった後に、ご自身の意思に基づいて遺産の分け方について書き記したものですから、法律上有効な遺言書である場合は、その内容にしたがって相続財産を分ける必要があります。
他方で、もし遺言書が無効である場は、その遺言書の内容に従う必要はなく、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
そのため、遺言書が有効であるのか無効であるのかはまずチェックすべきポイントです。
遺言書が有効か無効かをどのように見分ければよいか解説します。
方式のチェック
遺言は、遺言を作成した方が亡くなったときに法律上効力が発生します。例えば、不動産の所有権が特定の人に移転するなどの法律上の効果がすることになります。そのため、単なるメモ書きのような紙やあいまいな内容である場合は、遺言として扱われない場合があります。
法律上、大きく分けて、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。
細かくいえば、「秘密証書遺言」、「一般危急時遺言」、「難船危急時遺言」、「一般隔絶地遺言」、「船舶隔絶地遺言」等もございますが、この記事では割愛します。
自筆証書遺言と公正証書遺言とではチェックするポイントが異なりますので、それぞれを解説します。
自筆証書遺言は、誰でも簡単に作成できるというメリットがありますが、他方で、上記要件を欠いてしまうと法律上無効になってしまい、せっかく作成した意味がなくなってしまうというデメリットがあります。
なお、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも可能になりました(他の部分は自筆が必要ですのでご注意ください)。
また、遺言書を一度作成したものの、一部を変更したいという場合の方法も法律に定められています。
まず、遺言者が、変更した箇所に、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません。
公正証書遺言の場合についても、、法律の専門家である公証人が作成しますから、方式違反で無効になることは考えにくいところです。厳格にいえば、証人として不適格である人が立ち会っているか証人の人数が不足していないか、署名押印はあるのか等をチェックすることはありますが、実際上はそのような方式違反になるということは現実的にはありません。
遺言能力のチェック
遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足りる意思能力をいいます。
遺言者にこの「遺言能力」がなければ、その者が作成した遺言は無効となります。この遺言能力は、遺言書を作成した時点で必要になります。そのため、遺言書作成後に遺言能力が回復したとしても、作成時点で遺言能力を欠いている場合は、無効となってしまいます。
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、遺言者にこの遺言能力があることが大前提です。遺言者が高齢である場合や、特に認知症等の認知機能の低下があった場合には、この遺言能力の有無が争われて、相続人間で紛争になることが多くあります。
それでは、この遺言能力の有無はどのように判断するのでしょうか。
遺言能力の有無は、①医学的な所見、②遺言者の特性や言動、③遺言作成に至る経緯や内容、④遺言者と相続人(受遺者)との人的関係等を総合的に考慮して判断します。
もっとも、単に認知症と診断されているだけで遺言能力が否定されることはありません。
医療記録の中に長谷川式簡易知能評価スケール改訂版(HDS-R)の検査結果がある場合には、その検査結果をみてみましょう。
この検査は30点満点で測定され、目安としては、20点以下の場合には遺言能力に疑いが生じます。
認知症と診断されている場合は、20点以下は軽度、11~19点が中等度、10点以下で高度と判定されます。
もっとも、この検査結果があるからといって、それのみによって遺言能力が判断されるわけではありません。長谷川式テストは簡易なものですし、その時々により点数が変化する場合があるためです。
他の医療記録や看護記録等から当時の遺言者の遺言能力を検討する必要があります。
そのため、遺言書の内容もチェックする必要があります。
もっとも、だからといって、「90歳以上だから判断能力はない」「65歳だから判断能力がある」等と安易に判断するのではなく、上述したように、医療記録等を慎重に検討する必要があります。
このように、遺言書を作成するに至った経緯や内容、関係性等も、遺言能力を判断する上では重要なポイントです。
遺言の無効を主張されている(または、主張したい)場合は?
遺言が無効である可能性がある場合、どのようにして遺言無効を主張するのでしょうか。もちろん、話し合いによる遺産分割協議ということも考えられますが、話し合いでまとまらない場合には、法的な手続として遺産分割の前提を争うための遺言無効調停と民事訴訟が考えられます。
遺言無効調停
まずは、遺言無効調停を申し立て、調停手続の中で遺言が無効であることを主張します。調停とは、裁判所が介入して行う話し合いです。
当事者同士の話し合いで解決しなかったことでも、裁判官が、双方の意見を聞き、遺言の有効性について裁判所の意見を述べることによって、訴訟によらずに話し合いで解決する可能性があります。
民事訴訟
遺言無効の調停によっても、解決に至らなかった場合、いよいよ訴訟となります。具体的には、まさに遺言が無効か否かについて判決をもらう遺言無効確認請求訴訟を提起することとなります。
なお、この民事訴訟を提起するためには、必ず訴訟提起をする前に調停を申し立てたことがあることが必要となります。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
これらの調停や訴訟の手続は、ご本人で行うことはできますが、専門的な知識や戦略性が要求されることとなるので、手続が煩雑であったり、言いたいことがうまく裁判官に伝わらなかったりするおそれがあります。弁護士であれば、依頼者様のお話をよく聞いた上で、その内容をまとめ、効果的に裁判官に伝えることが可能です。
遺留分が侵害されている!
遺留分とは相続財産について、一定の相続人に最低限の相続財産を受け取ることができるよう保証する制度をいいます。
本来は相続財産をどのように処分するかは被相続人が生前に自由に決めることができます。例えば、特定の一人に全て相続させることもできます。しかし、相続財産は、相続人の生活保障となる場合があります。被相続人の自由な意思に任せてしまうと、残された相続人の生活が脅かされてしまう場合があります。
そこで、相続財産の一定割合については、一定の相続人に対してきちんと確保しなければならないとされているのです。
なお、注意しなければならないのが、遺留分は遺言書が存在するときに問題となるものという点です。遺言書がなく遺産分割協議を行う場合には問題にはなりません。遺産分割を行う場合は、法定相続分を一つの目安として、協議を進めていくことになります。
よくあるケースは、親が特定の子1人のみに相続財産を承継させる場合です。この場合は、配偶者や他の子が遺留分を主張します。
また、夫(父)が愛人に対して財産を全て贈与するという場合もあります。夫(父)が会社の経営者等で、夫婦仲がうまくいっていない場合に、愛人に贈与するケースがあります。長年連れ添った妻からすれば許しがたい行為であり、子どもたちからしても到底納得がいくものではありません。
このようなケースで遺留分を主張していくことになります。
遺留分を請求できるのは、①配偶者、②子(または代襲相続人)、③直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の請求には消滅時効が定められています。
まず、「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年を経過すると、消滅時効により請求できなくなってしまいます。
かりに、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知らなかったとしても、10年の経過により消滅時効により請求できなくなります。つまり、相続開始から10年経つと遺留分について請求ができなくなるのです。
遺留分を請求する場合は、まず書面で通知をすることをお勧めします。相手に対して遺留分の請求していることをきちんと形に残すためです。その後、相手方と交渉をするのが多いでしょう。
それでも話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
調停は話し合いでの解決ですから、話し合いがまとまらない場合は、裁判を利用することもあります。
自分で遺言書を見つけた場合は?
自筆証書遺言を発見した場合は、家庭裁判所から「検認」の手続きを受ける必要があります。これに対し、公正証書遺言については、検認手続は不要です。また、令和2年7月より、法務局で自筆証書遺言を保管する制度がスタートしています。この法務局で保管される自筆証書遺言については、検認は不要です。
検認は、遺言の保管者が相続の開始を知った後、遅滞なく、相続開始地の家庭裁判所に提出して行う必要があります。
封がされている遺言書は、家庭裁判所で、相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。
遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり、検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外において遺言書の開封をした場合には、五万円以下の過料に処される可能性がありますので注意しましょう。
遺言書を隠匿した場合には、相続欠格といって、相続する資格を失う可能性がありますので、注意しましょう。
検認は、発見当時の遺言書の状態を家庭裁判所が記録することにより、その語に偽造などをされることを防ぐために行います。そのため、検認手続きを経たからといって、遺言書が有効になるわけではありませんし、裁判所が有効であることのお墨付きを与えたことにはなりません。
ただし、金融機関等も検認を経ていない遺言書をもとに相続手続きに応じないことが通常ですから、まずは検認手続きの申立てを行いましょう。
家庭裁判所に検認の申立てをすると、裁判所は、申立人と相続人に対して検認期日の日時などを知らせる通知書を郵送します。この通知書をみて、他の相続人は遺言書の存在を知ることになるのです。なお、相続人の立ち会いは任意ですので、必ずしも出席しなければならないというわけではありません。
検認期日では、相続人立ち会いのもと、裁判官が遺言書を開封し、遺言書の方式や文字が書かれたペンの種類等細かな点もチェックし、「検認調書」を作成します。裁判所は、相続人に対し、遺言書が遺言者の自筆であるか、また、遺言者の押印であるかどうかが確認されます。
検認手続が終わると、裁判所が検認したことを証する証明書を添付して、遺言書が返還されます。
弁護士に任せることで負担が大幅に軽減されます
遺言書がある場合であっても、家庭裁判所に検認の申立てをしたり、また、その有効性に関して相続人間でもめてしまう場合があります。
このような手続きやもめごとは、相続人にとって大きな負担となります。
当事務所の弁護士はこのような相続問題について精通しておりますし、弁護士は代理権限がありますから、遺言書の有効性について調査を行ったり、代理人として有効性について主張反論をすることもできますし、検認手続きの申立てを代理で行うこともできます。