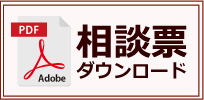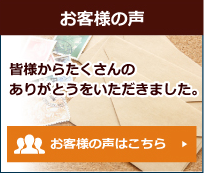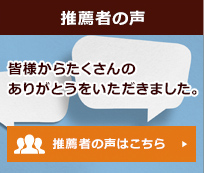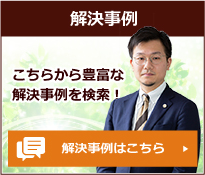【解決事例】所在等不明共有者持分の取得決定が認められた事案
事案の概要
元々、土地と建物とが父と次男の共有でした。父の死亡により長男が父の共有持分を取得しました。
その後、次男が死亡したものの、借金などがあったため、相続人である長男が相続放棄をしました。
その後はしばらく自宅は空き家のまま放置していたのですが、固定資産税の負担などから、自宅を処理することにしました。
しかし、登記簿上は長男と亡次男の共有になっており、亡次男には相続人が不存在の状態であるため、簡単に処分することができません。少なくとも、亡次男の持分を長男が取得するなどの対応が必要です。
このような状態で当事務所にご依頼されました。
弁護士の活動
本件は令和3年の民法改正で新設された「 所在等不明共有者持分の取得決定」という制
度が使えると考えました。
同制度は民法 262 条の2に定められています。
| ※参考条文 民法262条の2 (所在等不明共有者の持分の取得) 第二百六十二条の二 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において 所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。 この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させる。 |
この制度は「 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」と定められていますが、すでに共有持分権者が死亡し、相続人が不存在の場合も含まれます。
まず登記や戸籍等を収集し、本件で共有持分権者に相続人がいないことを調査しました。
その上で、依頼者の方から事情をお伺いし、裁判所に申し立てをするための申立書などを作成しました。
並行して、複数の不動産業者に対して不動産の査定を行なってもらい、その査定書をもとに、本件物件の価値(共有持分に相当する価値)を算定しました。
裁判所に申し立てを行い、こちらが想定する金額での取得決定を得ることができました。同決定に基づき、依頼者の代わりに法務局にて供託を行い、それを裁判所に提出しました。
裁判所から取得した書面などを司法書士に提供し、所有権移転登記手続きを完了しました。
担当弁護士の所感
依頼者の方から空き家になっていた「 負動産」が無事に売却ができるようになってよかったとお喜びいただきました。
「所在等不明共有者持分の取得決定」の事案は新潟地方裁判所でもまだ事案の蓄積が少なく、情報も少ない状況でした。
無事に滞りなく共有持分を取得することができ、大変よかったです。(担当弁護士 五十嵐勇)
掲載日2025年4月7日
五十嵐 勇
最新記事 by 五十嵐 勇 (全て見る)
- 【解決事例】所在等不明共有者持分の取得決定が認められた事案 - 4月 7, 2025
- 【解決事例】法定相続人20名以上の遺産分割の事例 - 12月 3, 2024
- 【解決事例】消滅時効の援用通知を行った事例 - 9月 27, 2024
関連記事はこちら
- 【解決事例】遺産分割事件で多額の請求をされたが、大幅に減額して解決した事案
- 【解決事例】相続放棄を行った事例
- 【解決事例】相続人以外の者に遺産を全て遺贈するとの遺言が存在したことから遺留分侵害額請求を行い、2000万円以上の金銭を取得した事例
- 【解決事例】親族と関係を持ちたくないため相続放棄を行った事例
- 【解決事例】法定相続人20名以上の遺産分割の事例
- 【解決事例】被相続人が所有していた建物の管理が困難であるため、相続放棄を行った事例
- 【解決事例】遺産分割調停を申立てた後、遺産となる不動産全てを売却し、調停が 成立した事例
- 【解決事例】不動産の価値を0と評価して、不動産以外の財産は2分割した事例
- 【解決事例】相続人の間で遺産の分割方法に争いがないケースにおいて、弁護士が 遺産分割協議書を作成して預金の解約等を行った事例
- 【解決事例 相続】解体費用がかかる建物を取得せず、預貯金だけを取得できた事案
- 【解決事例】消滅時効の援用通知を行った事例
- 【解決事例】遺産分割において、使途不明金の一部を相手方が取得したことを認めさせた事例
- 【解決事例】相続放棄を行った事例
- 【解決事例】連絡がとれない他の相続人に連絡をとり、無償で相続分譲渡を受けた事案
- 【解決事例】相続放棄を行った事例
- 被相続人の預金口座から使途不明な出金があった事例
- 相続人を調査した上で自筆証書遺言の検認申立てをした事例
- 相続手続 速やかに相続手続を行った事例
- 遺留分に相当する金銭について速やかに取得した事例
- 相続の承認又は放棄の期間伸長の申出を行った上で、被相続人の負債 を調査した事例
- 【解決事例】遺産について調査を行い、適正な割合で遺産分割を行った事例
- 清算人の申立てを行い、不動産売買を実現した事案
- 【解決事例】遺産分割協議 多数の相続人と協議をした事例
- 【解決事例】法定相続分の一部を早期に取得した事例
- 【解決事例】公正証書遺言(予備的遺言)の作成を行った事例
- 【解決事例】公正証書遺言の作成を行った事例
- 【解決事例 相続放棄】相続放棄期間経過後に相続放棄の申し立てをして、認められた事例
- 【解決事例 遺産分割】海外在住の依頼者から依頼を受け、不動産等を売却した事案
- 【解決事例】相続人3名から依頼を受け、代理で相続放棄の申述を行った事例
- 【解決事例】遺産分割調停において、預金の取引履歴(払出伝票等)を調査を行い、相手方が受領した生前贈与が認められ、獲得額の増額に成功した事例
- 【解決事例】遺産分割協議において、不動産等は承継せず、現金と預貯金等の流動資産を獲得することに成功した事例
- 【解決事例】相続人・相続財産調査のご依頼をいただき、債務等を調査した事例
- 【解決事例】東京の共有持分買取業者による共有物分割請求に対して、代償金を大幅に減額した上で共有持分の取得をする内容での和解が成立した事例
- 【解決事例】相手方に遺留分侵害額請求を行い、交渉で約3800万円を獲得した事例
- 相続人が全員相続放棄をしつつ、被相続人の自宅内の動産類を処分することができた事例
- 賃借人(株式会社)の代表取締役が死亡し、賃借人の誰も明渡に協力しない中で、テナントの明渡を実現した事例
- 遺産分割調停で被相続人が保有していた自社株式(非上場株式)を後継者が全て取得して、経営権を維持することができた事例
- 入院されている方の財産管理のため成年後見人の申立てを行った事例
- 遺産分割協議 不利な遺産分割内容で応じるようにされていたが、弁護士が介 入することで公平な分割内容を実現できた事例
- 公正証書遺言の作成を行った事例
- 当事務所が遺言執行者として遺言書の内容を実現した事例
- 相手方に遺留分侵害額請求を行い、交渉で約1700万円を獲得した 事例
- 特別縁故者-特別縁故者として、被相続人の財産から7000万円の財産分与を受けた事例
- 遺留分-交渉にて遺留分侵害額の満額の支払いを受けた事案
- 遺産分割協議-交渉にて法定相続分に相当する金銭の支払いを受けた事例
- 遺産分割協議-親子間の遺産分割の事例
- 相続解決事例
- 相続調査-相続調査を行い、相続人と相続財産等が明らかになった事例
- 遺産分割- 不公平な内容で一方的に遺産分割が進められていた中で、当事務所 が代理人として協議し、不必要な不動産の取得を拒み、法定相続分に相当する代 償金を取得した事例
- 相続手続-相続財産調査を行った後、相続手続を行った事例
- 遺産分割協議-意図しない相続人がいた事例
- 相続放棄-相続人全員について放棄を行った事例
- 相続放棄-依頼後約2週間で相続放棄が受理された事例
- 遺産整理- 遺産の不動産を売却し、法定相続分どおりに分割した事例
- 相続で取得した土地に付いている抵当権を消滅時効援用通知で解消できた事例
- 遺産分割 長年にわって解決されなかった数次相続を解決した事案
- 収益物件について民事信託を設定した事例
- 遺産分割調停-調査の結果、相手方が被相続人から生前贈与を受けていることが判明したため、贈与分を相手方の特別受益として遺産分割を行った事例
- 遺産分割協議-遺産調査を速やかに行い、早期に解決できた事例
- 使途不明金-相続人から被相続人の預金に使途不明金があるとして、その返還請求をされた事例
- 遺産分割協議-弁護士が交渉し、疎遠となっていた相続人と遺産分割協議が成立した事案
- 遺産分割協議-弁護士の交渉により、疎遠な相続人と早期に遺産分割協議が成立した事案
- 遺産分割調停-弁護士が調停を申し立て、多数の県外在住の相続人と遺産分割調停が成立した事案
- 遺産分割調停-代償金を支払うことなく遺産を全て取得できた事例
- 遺産分割-弁護士の交渉により、自宅の土地建物を相続でき、早期に解決できた事例
- 遺産分割交渉-使途不明金が問題になったが、交渉で早期に解決できた事案
- 遺産分割調停-不動産を取得する代わりに支払う代償金の支払方法が問題となった事例
- 遺産分割協議ー遺産内容を相手方に丁寧に説明し納得してもらい、早期に解決できた事例
- 遺産分割調停-不動産を取得する代わりに支払う代償金の支払方法が問題となった事例
- 遺産分割協議-感情的対立がある場合に交渉により解決した事例
- 遺留分-訴訟にて遺留分侵害額に相当する約600万円の支払いを受けた事例
- 遺産分割協議-高額な特別受益について、交渉で勝ち取った事例
- 遺産分割調停-生命保険の受取人変更、不動産評価が問題となった事例
- 遺産分割協議-相続財産調査後、交渉により解決した事例
- 遺産分割協議-双方代理人関与のもと交渉により解決した事例
- 遺留分-感情的対立がある場合に交渉により解決した事例
- 遺言書作成-依頼者の希望に添った公正証書遺言を作成した事例
- 遺留分-使途不明金がある事案について約280万円増額した事例
- 遺言書作成-相続紛争を避けるために公正証書遺言を作成した事例
- 遺言書作成-子の生活に配慮した公正証書遺言を作成した事例
- 遺産分割協議-交渉により早期に遺産分割協議を成立させた事例
- 遺産分割協議-相続人調査と遺産分割協議書の作成を行った事例
- 遺留分-遺留分侵害額に相当する約600万円の支払いを受けた事例
- 遺言書作成-字が書けない方について公正証書遺言を作成した
- 死因贈与-死因贈与契約を立証し、預金の払い戻しを受けた事例
- 不当利得-預金の使い込みをした相続人から返還を受けた事例
- 相続税-土地境界の確定による相続税の更正をした事例